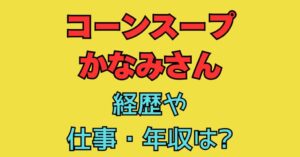年末恒例の歌の祭典であるNHK紅白歌合戦。
その年に人気の楽曲が多く披露される紅白歌合戦で、なぜボカロ(ボーカロイド)は出ないのでしょうか。
紅白歌合戦とボカロの関係性を、AdoさんやYOASOBIとの関係性も踏まえて、まとめていきます。
紅白にボカロが出場しない本当の理由
紅白歌合戦にボカロが出演しないのは、何か理由があるのでしょうか。
紅白の出演条件についても気になりますね。
紅白歌合戦にボカロが出演しない理由について、権利やテレビとの相性など様々な視点から考察していきます。
紅白の出演条件とは
紅白歌合戦の出演条件は、モデルプレスによると「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画・演出」の3つの点を中心に、総合的に判断しているんだそう。
「今年の活躍」については、CD等の売り上げ、インターネットのダウンロード・ストリーミング・ミュージックビデオ再生回数・SNS等についての調査から判断しているとのこと。
しかし、たとえ売り上げや話題性が高くても、企画に合わなければ選ばれないことがあります。
ボカロを取り巻く権利や制作の仕組み
初音ミクの登場の仕方や曲が終わったあとの消え方
— ただ初音ミクを語る (@VOCALOID_20831) October 10, 2025
今のマジカルミライではほとんどがキラーンという音とエフェクトになりますが、
・キャラクターを一人の人間として扱ってみたライブ
・電子の歌姫という言葉を忠実に守り抜いたライブ
表現は間違っているのかもしれませんが過去のライブを2つほど pic.twitter.com/WwIzBE2Nik
ボーカロイド(ボカロ)は、音楽業界の中でも、権利や制作に関して特異な構造をもっています。
ボカロは、ヤマハが開発した音声合成技術で、声優や歌手の声を録音して作られた音声ライブラリから、制作者(ボカロP)が楽曲を制作しているそう。
つまり、サンプリング音源をもとに誰でもPCだけでつくることができるのが、ボカロなのです。
そのため、著作権は通常の楽曲であれば、レコード会社にあるのに対し、ボカロは制作者にあるということ。
また、初音ミクなどのキャラの肖像権・商標権は別に存在。
このように、通常の楽曲とは異なり、ボカロは音源・キャラ・映像のすべてに許諾が必要になるので、紅白歌合戦のような全国放送ともなると調整が煩雑になります。
テレビとの相性の問題
テレビでの主要な音楽番組では、「生放送・生歌唱」が基本であり、歌手の生の感情やパフォーマンスを見せることが重視されます。
そのため、事前に打ち込んだ歌声を再生するボカロは、ライブ感を見せる演出がとても難しいよう。
また、紅白歌合戦は、出演者=人格という前提があるので、人格を持たないボカロを出演者として扱うのは、多くのハードルがあります。
NHKの「出演者に対する人権尊重ガイドライン」では、出演者の人格・人権を尊重することが明記されており、人格・人権を持たないバーチャルキャラの出演は想定されていないよう。
さらに、ボカロのテレビ出演には、権利処理も煩雑であるため、その難しさもあります。
このように、ボカロがテレビに出演するには、多くのハードルがあるようですね。
視聴者のイメージとのギャップ
紅白歌合戦の視聴者層は、特に幅広くなっており、ボカロ文化になじみのない層も多いです。
そのような人たちにとって、人格がないボカロは「誰が歌っているのか」「どうやって歌っているのか」という疑問を持たれやすく、番組側はその説明をしなければなりません。
また、ボカロと歌手とでは、表現方法や楽しみ方が大きく異なるよう。
歌手は、衣装や表情、歌い方などを工夫し、視聴者はそれを見て楽しみますよね。
それに対し、ボカロは映像の見せ方や編曲技術を楽しむことになり、大きなギャップがあります。
ボカロのイメージが視聴者にしっかり浸透しないと、紅白歌合戦のような大きな番組への出演は難しいかもしれませんね。
ボカロ曲が紅白で歌われたこともある?
これまでボカロ曲が紅白歌合戦で歌われたことはあるのでしょうか。
当時の視聴者からの反響も気になりますよね。
紅白歌合戦で歌われたボカロ曲や、当時の反響についてまとめていきます。
紅白で披露された意外な曲
ボカロ曲が紅白歌合戦で披露されたことはあります。
ニコニコ動画でも活動していた小林幸子氏がこの時紅白で千本桜を歌ったのが、初の紅白で歌われたボーカロイド曲かな?
— マヨくん (@vaD80wyV2x0QPJx) January 11, 2025
まふまふが命に嫌われているを歌ったのは21年の紅白だから pic.twitter.com/fKIz9IxhEk
しかし、ボーカロイド(初音ミクなど)が直接出演して歌ったわけではなく、人間の歌手がボカロ曲を歌唱する形で披露されました。
・「千本桜」(作詞・作曲:黒うさP)
歌唱者:小林幸子(第66回 2015年)
初音ミクの代表曲を、豪華衣装で歌唱。
・「命に嫌われている」(作詞・作曲:カンザキイオリ)
歌唱者:まふまふ(第72回 2021年)
ボカロPが制作した楽曲を、歌い手まふまふが高温ボイスで歌唱。
出演が難しいボカロですが、歌手とボカロがコラボすることで、紅白歌合戦という場に適合させたのですね。
当時の反響と反応
ボカロの曲が披露されたことに対して、演出全体に対して賛否あったようですが、肯定的な意見も多かったよう。
まず、2015年に小林幸子さんが「千本桜」を披露した際には、巨大な小林幸子像とニコニコ動画風の弾幕演出という派手な演出で、「ネット文化を取り込んでいる」と話題になりました。
しかし、一方では紅白の伝統とかけ離れた演出と、年末の家族番組に合わない曲調に疑問を持たれたそう。
2021年にまふまふさんが「命に嫌われている」を披露した際には、その「歌ってみた」文化に賛否の声が上がりました。
まふまふが出場していた頃の紅白 pic.twitter.com/4hzQ1h9CIz
— ちょっと昔のものbot (@bot12536) December 31, 2024
ネットでは当たり前になりつつある、歌い手による「歌ってみた」文化が紅白歌合戦に登場したことで、若年層やファンからは喜びの声が上がったよう。
一方で、見慣れない視聴者からは、まふまふさんのビジュアルや演出に戸惑った人も多かったようです。
それでも“ボカロ本人”が出ない理由
🔬ボカロ紅白ラボ ダイジェスト🔬
— ボカロ紅白歌合戦 (@vocakouhaku) August 29, 2025
前向きで明るくて元気を与えてくれた『奇跡さえも』を振り返り
優雅な踊り、ハモリの綺麗な歌声で良さが最大限に引き出されたミクの姿をお楽しみください#ボカロ紅白ラボ #ボカロ紅白歌合戦 pic.twitter.com/HW5cwvPDzn
これまでの紅白歌合戦で、ボカロ曲が広く知られるようになったと言っても、まだ視聴者層とのギャップは大きいよう。
権利の問題も未だ確立されていません。
それに加え、ボカロ本人がステージに登場するには、ホログラムやARなどの特殊演出技術が必要になります。
生放送である紅白歌合戦は、その演出安定性に課題があるそう。
そのため、まだボカロ本人が出演するのは先になりそうです。
AdoやYOASOBIはどう違うのか
紅白歌合戦で出演し話題になっているAdoさんやYOASOBIは、ボカロとどう違うのでしょうか。
2組がボカロ文化とどのようなつながりがあるのかも気になりますね。
AdoさんやYOASOBIとボカロとの関係性についてまとめていきます。
紅白と相性が良い理由
AdoさんやYOASOBIが紅白歌合戦によく出演しているのは、両者がボカロ的な表現スタイルを持っていながらも、テレビ出演に適応しやすい構造を持っているから。
まず、Adoさんは顔出しをしていないという特徴がありますが、実在する人物ではあるので、他の歌手と同じように契約・出演が可能。
また、顔出しはしていなかったとしても、声に感情を乗せて届けるスタイルが、テレビのライブ感に合うよう。
YOASOBIは、歌のスタイルはボカロに寄せていながらも、顔出しをしており、生歌唱で表現されているので、他の歌手と同等に扱うことができます。
さらに、両者とも知名度が高く、若年層だけでなく親世代にも認知されているのは、大きなポイントでしょう。
これらの点から、AdoさんやYOASOBIは、紅白歌合戦と相性が良いのだと考えられそうです。
ボカロ文化とのつながり
AdoさんとYOASOBIは、どちらもボカロ文化をルーツに持っているという特徴があります。
まず、Adoさんはボカロ曲をカバーして配信する「歌ってみた」活動からキャリアをスタートさせたとのこと。
自身の歌ではないボカロの曲を歌うことを、活動の中心としてきており、今でも「うっせえわ」「唱」など、ボカロP(ボカロ曲製作者)とコラボして生まれた楽曲が多く出しているよう。
「うっせぇわ」や「唱」など、ボカロPとのコラボレーションで数々のヒット曲を飛ばしたAdoは、ボーカロイド曲をカバーして配信する「歌ってみた」が活動のきっかけ。
THE FIRST TAMESより引用
YOASOBIもボカロとつながりが深く、作曲担当のAyaseさんは元々ボカロP(ボカロ曲製作者)として活動していたとのこと。
そのため、YOASOBIの楽曲は、物語性や歌の構成などにボカロの文化が取り入れられたものになっています。
Ayaseさんは、インタビューの中で「今の僕はボカロがないと存在しない」「ボカロをやってきたことが自分のベース」と語っていました。
どちらもボカロ文化を継承しながら、人気となったのが特徴的ですね。
“ボカロ的存在”としての立ち位置
やっぱ紅白のAdoちゃんかっこいいよなぁ
— さえもんさ/オマエタチ🥀🥀🥀💙💙💙 (@saemon0221) April 24, 2025
能舞台で歌唱ってのがまたカッコいい‼️#NHKMUSICSPECIAL_Ado pic.twitter.com/WvapKliGk2
AdoさんやYOASOBIは、ボカロ的存在としての立ち位置を確立していると言えそう。
ボカロは人格がなく、合成された音声のキャラクターですが、AdoさんやYOASOBIは実際の人が歌唱しているので、その点では違っています。
しかし、ボカロのもつ楽曲制作者と歌唱者が違うという点や、映像演出を重視している点、感情表現がネット的である点など、ボカロの要素を多く持っているそう。
特に、Adoさんの「うっせぇわ」の若者の怒りを激しく表現している点や、YOASOBIの「夜に駆ける」で死生観を描いている点などが、ネットの特徴的な表現であるよう。
過去に紅白歌合戦に出演したまふまふさんの「命に嫌われている」も、披露した際にはそのネット的な世界観で、慣れない層からは戸惑いの声があったとのこと。
このように、実在の人が歌唱している以外はボカロの要素を多く持っているので、AdoさんやYOASOBIはボカロ的存在と言われているようです。
紅白に変化の兆しはある?
紅白歌合戦は今後どのように変化していくのでしょうか。
ボカロが出演できるようになるのかも気になりますね。
今後の紅白歌合戦の変化の可能性についてまとめていきます。
演出や技術の進化
紅白歌合戦の演出や技術は、時代とともに大きく進化してきました。
2009年のNHK技研だよりには、21台のカメラを駆使する「ミリ波モバイルカメラ」が紹介されており、2024年には、それが進化した「ミリ波4Kワイヤレスカメラ」が活躍したんだそう。
これにより、自由自在なカメラワークが可能になりました。
また、2017年からは、舞台上に巨大なLEDスクリーンが登場し、これにより映像表現の幅が広がったよう。
昨年の第68回紅白歌合戦では、左右の花道からメインステージまで舞台全面に広がる巨大なLEDスクリーンが登場した。
VIDEO SALON.webより引用
LEDスクリーンになったことで、映像に奥行きを出すことができ、楽曲に合わせた世界観を作りやすくなったそうです。
歌唱そのものだけでなく、楽曲に合わせた映像演出もこれからの楽しみになりそうですね。
バーチャルアーティストの存在
実在の歌手ではないバーチャルアーティストの存在は、これからの紅白歌合戦の進化を促していきそう。
まず、出演者の定義がバーチャルアーティストによって、広がることになるでしょう。
これまでは、「出演者=人間」でしたが、バーチャルアーティストの存在で、演出自体が出演者という定義に変わりそうです。
また、バーチャルアーティストの出演のために、AR・ホログラム・CG・リアルタイム合成などの技術が必要になるため、それらの技術が向上していくことになりそう。
さらに、視聴者のもつ紅白歌合戦のイメージも大きく変わっていくでしょう。
このように、この先バーチャルアーティストが有名になっていくと、紅白歌合戦にも多くの変化が生まれそうです。
今後の可能性
今後の紅白歌合戦は、これまでのものから大きく変化していくものと考えられます。
まず、バーチャルアーティストやVtuberのような、実在しない人物が出演していくことになりそう。
それにより、演出技術の幅が広がり、世界中の場所との中継や、仮想空間など紅白歌合戦の舞台はNHKホールという空間から大きく広がっていくでしょう。
また、ジャンルの壁もなくなり、演歌・J-POP・ボカロなど様々なジャンルが融合したパフォーマンスも増えていきそう。
紅白歌合戦が長年受け継いできた伝統と、最新の流行をどのように織り交ぜ進化させていくのか、楽しみですね。
まとめ
今回は「紅白にボカロが出場しない本当の理由!AdoやYOASOBIが代わりになった?」
〇紅白にボカロが出場しない本当の理由
〇ボカロ曲が紅白で歌われたこともある?
〇AdoやYOASOBIはどう違うのか
〇紅白に変化の兆しはある?
についてご紹介させていただきました。
実際にはどうなるのか注目ですね!