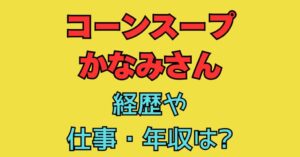長部訓子(おさべ くにこ)さんは、伝統的な酒造メーカー「大関株式会社」の代表取締役社長。
そんな長部訓子さんは、どんな人物なのか気になりますね。
長部訓子さんのプロフィール・経歴から長部家の歴史についてもまとめていきます。
長部訓子のプロフィール
大関株式会社の社長・長部訓子さんは、どんな人物なのでしょうか。
プロフィールだけでなく、人柄も気になりますよね。
長部訓子さんの情報について、人柄も含めてまとめていきます。
生年月日や出身はどこ?
大関 日本酒は食文化のひとつ、「人と人とをつなげて、心と体を温める」/長部訓子社長インタビュー(食品産業新聞社ニュースWEB) https://t.co/HtqoKv1S4C pic.twitter.com/rjZvWA4pkq
— .header (@splatoonCH) June 16, 2021
長部訓子さんの生年月日は、1957年3月22日で、2025年8月現在は68歳。
出身地については、明確な記載は見つかりませんでしたが、兵庫県出身の可能性が高いです。
その理由としては、長部訓子さんが社長を務める「大関株式会社」が、兵庫県西宮市に本社を置いており、長部家も代々兵庫県にゆかりがある家系のため。
兵庫でどのような生活を送ってきたのかも気になるところですね。
出身大学や学歴について
おはスコ( ˘o˘ )♪#2024大関蔵開き
— SAYOKOチャンネル (@s_y_Singer) March 9, 2024
何千人の方が来られたかはわかりませんがみんなで「酒は大関心意気」
真ん中の白い法被の方が私の大好きな長部訓子社長です❣️❣️❣️
楽しい蔵開きでした✨👏
たくさんの笑顔見れました😆
世界を笑顔に❤️
#蔵開き #灘五郷 #日本酒 pic.twitter.com/VUvSSYRwZ2
長部訓子さんの学歴については、「1973年に甲南女子高等学校を中退」したという情報が確認できました。
その後については、「閨閥学」や「歴代社長」サイトによると、大学への進学はされていないよう。
高校中退後は、1988年にロングエステート(現・大関エステート)の取締役に就任し、2003年には大関株式会社の社外監査役、そして2017年には社長に就任しています。
学歴よりも実務経験と家系的な背景を活かして、キャリアを築いてきたタイプの経営者のようですね。
人柄やエピソード
長部訓子さんの人柄は、歴史への敬意と責任感が分かるエピソードから伝わってきます。
まず、長部訓子さんは2021年に、大関創業家である長部家の墓を京都から西宮に移すという改葬を一人で進めました。
叔父の長部文治郎さんから託された仕事だったそうで、仕事を行う過程で改めて、今まで積み重ねられてきた長い歴史を「重い」と感じたそう。
その経緯もあって、「SAKETIMES」のインタビューの中からは、長い歴史を持つ会社を継いだ社長としての覚悟が感じられました。
大坂屋という屋号で酒造りを始め、『新しい事業を大きく育てよう』と覚悟を決めた先人の精神に今一度立ち戻って、考えなければいけない。そういう、私たち自身に向けたメッセージにしたいのです。
SAKETIMESより引用
伝統を守るだけでなく、それを現代に生かし、さらに成長させていこうとする姿勢が印象的ですね。
長部訓子のこれまでの経歴
長部訓子さんは、どのような経緯で大関の社長になったのでしょうか。
創業家の長女である長部訓子さんなので、自然な流れだったのだろうかと想像してしまいますね。
長部訓子さんのこれまでの経歴についてまとめていきます。
大関に入ったきっかけ
長部訓子さんが大関に関わるようになったのは、創業家の一員としての責任感によるものだと考えられます。
長部訓子さんは元々マーケティング会社などで働いていましたが、1988年に大関の関連会社であるロングエステート(現・大関エステート)の取締役に大関家の一員として就任。
創業家を受け継いでいく責任感から、家業の一端を担うポジションに携わるようになったのではないかと考えられます。
その後、ロングエステート取締役の経験から、経営感覚や組織運営の基礎を学び、キャリアアップを重ねていきました。
社長になるまでの歩み
毎日の晩酌のお供に「大関 純米酒」を🍶
— 大関|日本酒メーカー🍶 (@ozeki_jp) August 29, 2025
大関オリジナル酵母で仕込み、発酵過程を緩やかにすることで、飲みやすくマイルドな口当たりと飲みごたえを感じるコクのある後味を実現🙌
毎日飲める美味しさ&大容量で、皆さんの食卓に優しく寄り添います◎ pic.twitter.com/Tj48SDGpew
長部訓子さんが大関株式会社の社長となるまでの歩みをまとめます。
・ロングエステート取締役(1988年)
・イージーネット入社(1995年)
・イージーネット取締役/大関社外監査役(2003年)
・大関取締役(2015年)
・大関専務(2016年)
・大関代表取締役社長(2017年)
外部視点を得るためのイージーネット入社も含め、長部訓子さんは創業家の一員としての責任と、経営者としての実力を着実に積み重ねてきていることが分かります。
社長になった理由
大関が管理する、日本最古の現役灯台「大関酒造 今津灯台」や大関の酒蔵を作家の恩田陸さんに取材いただいた記事が文芸春秋「オール読物」9・10月号に掲載されました😄
— 大関|日本酒メーカー🍶 (@ozeki_jp) August 26, 2025
今津灯台は大関がある兵庫県西宮市、今津の港で200年以上前から、航海の安全を見守っています🚢
みなさん、ご存じでした? pic.twitter.com/BwoFWaEQGH
長部訓子さんが大関の社長に就任した理由は、家業の継承だけでなく、キャリアを着実に積んできたゆえの結果と言えそうです。
長部訓子さんは、大関創業家の長女として、歴史とブランドを守ろうとする責任感がありました。
それもあって、ロングエステート取締役就任をきっかけに、段階的に経営に携わるようになっています。
そのため、長部訓子さんは創業家の一員でありつつ、実務的にも正当なルートを踏んでおり、その結果としての社長就任だったと言えそう。
キャリアの中で培われた実務経験と、創業家の歴史を背負う覚悟を持った社長就任で、これからの成長に期待ができそうですね。
長部家の歴史とは
長部訓子さんが継承する長部家にはどのような歴史があるのでしょうか。
大関は、創業300年超えということなので、どのような変遷をたどってきたのかも気になりますね。
長部家と、長部家に深いつながりがある大関の歴史について、まとめていきます。
大関と長部家のつながり
/
— 大関|日本酒メーカー🍶 (@ozeki_jp) August 20, 2025
「全国燗酒コンテスト2025」で
金賞を受賞しました✨️
\
🥇お値打ちぬる燗部門:上撰金冠はこのさけ
甘さと辛さのバランスのとれた飲み飽きしない旨口の日本酒。
🥇お値打ち熱燗部門:大関 純米酒
マイルドな口当たりと飲みごたえを感じるコクが特徴◎
この秋冬に、ぜひ熱燗・ぬる燗でどうぞ🙌 pic.twitter.com/1w59rAKX8s
大関と長部家のつながりは、単なる「経営者と会社」の関係ではなく、創業家として300年以上にわたって酒造業を牽引してきた強い結びつきがあるよう。
大関の創業者は、初代・大坂屋長兵衛で、1711年に創業しました。
屋号は「大坂屋」でしたが、1884年に酒銘を「萬両」から「大関」に変更し、長部家が代々受け継ぎながら、名門酒造家として栄え続けていたよう。
大関はその後1935年に株式会社化しましたが、当時から2002年にかけても長部家が社長職を受け継いできていました。
また、当主は7代目以降「文治郎」を襲名してきており、その名を継ぐことで家系とブランドを維持しています。
大関と長部家の結びつきが強いことがよく分かりますね。
長部家が受け継いできた酒づくり
お盆休み、みなさんいかがお過ごしですか?🍆🥒
— 大関|日本酒メーカー🍶 (@ozeki_jp) August 15, 2025
帰省や旅行など、お出かけのお供におすすめなワンカップ。
コンパクトで持ち運びしやすくコンビニでもゲットできるので、お弁当と一緒に新幹線で…お出かけ先の公園で…など、ぜひ色々なところに連れて行ってくださいね😊 pic.twitter.com/WJqBmYbzqy
長部家が受け継いできた酒づくりとは、単なる技術の継承ではなく、「挑戦」と伝統技術への「信頼」が軸になっているようです。
初代・大坂屋長兵衛は1711年、冷蔵技術も分析機器もない時代に、腐敗リスクを背負って酒づくりに挑戦しました。
その挑戦に対して、長部訓子さんも畏敬の念を感じているよう。
もし腐らせてしまったらすべて無駄になってしまう。それだけのリスクがある先行投資型の事業をやろうとチャレンジしたことが、今の大関につながっています。
SAKETIMESより引用
そこで生まれた伝統技術に信頼を置きつつ、「ワンカップ大関(1964年)」などのさらなる挑戦によってより良いものにしながら技術を受け継いでいくことを、大関は大切にしています。
特に、長部家が受け継いできた伝統技術である「発酵技術」は、応用化され、他の食品や化粧品開発にも受け継がれています。
これまでの社長たちについて
大容量でたっぷり楽しめる、大関の「のものも」🍶
— 大関|日本酒メーカー🍶 (@ozeki_jp) August 14, 2025
料理酒としてお使いいただくことも多いですが、お米の旨味がしっかり感じられ、そのまま飲んでも美味しいんです😋
キリッとキレのある味わいなので、お肉などのスタミナ料理や濃い味の料理と相性バツグン◎ 晩酌のお供にも、ぜひどうぞ✨️ pic.twitter.com/BsbJp8PXJ8
大関株式会社の歴代社長は、創業家の長部家を中心に据えながらも、時代に応じて外部人材も登用するなど、柔軟性と伝統の継承を両立させてきたよう。
歴代社長について詳しくまとめると以下のようになります。
・初代 長部恒三郎(1935~1937):株式会社化を実行し、家業から企業体制へ移行
・2代 長部昇一(1937~1966):戦中・戦後の混乱期を乗り越え、灘の酒造業を再建
・3代 長部恒雄(1966~2002):「ワンカップ大関」を開発し、清酒の大衆化を牽引
・4代 橋本康男(2002~2010):創業家以外から初の社長。経営の近代化を推進
・5代 西川定良(2010~2017):ブランド再構築と海外展開を強化
・6代 長部訓子(2017~):創業家から再登板。「創家大坂屋」など文化的ブランドを立ち上げ
初代~3代目までは創業家が経営を担い、時代の流れの中で大関を受け継いできました。
特に、3代目長部恒雄さんの時代に生まれた「ワンカップ大関」は、それまでの一升瓶文化を覆す画期的な商品となったとのこと。
その後、経営の近代化を目指すべく、創業家以外から2人の社長を迎えました。
5代目の西川定良さんの時に、大関は海外市場に本格的に進出したよう。
そして、2017年から創業家である長部訓子さんが、原点回帰を掲げて社長に復帰しました。
大関は長部訓子さんの社長就任によって、また新たなステージに入ったのだと言えそうですね。
長部訓子のこれから
社長となった長部訓子さんは、大関をどのように導いていくのでしょうか。
日本酒業界が今どのような立場なのかも気になりますね。
長部訓子さんが目指す経営や、日本酒業界の今後についてまとめていきます。
どんな経営を目指している?
8月はお盆休みや帰省など、人と会う機会が多いシーズン🎐
— 大関|日本酒メーカー🍶 (@ozeki_jp) August 12, 2025
今月のご予定はもうお決まりですか?
「創家 大坂屋 純米大吟醸」は華やかさとコク・旨味を楽しめる逸品です。洋食・和食どちらにも馴染み、みんなでの食事シーンにもピッタリ◎
特別な日をさらに彩る1本に、ぜひ🥂 pic.twitter.com/2OhIAjLjde
社長である長部訓子さんが目指す大関の経営は、「歴史の継承」と「現代的価値の創造」を融合させたものになるでしょう。
それが分かるのが、長部訓子さんが始めた2つのブランドです。
1つ目が、「創家 大坂屋」で、初代・大坂屋長兵衛の屋号を冠しており、原点回帰の手仕込みの純米大吟醸。
2つ目が、新規事業開拓のために作られた「大関 醸す」で、発酵技術を活かした食品・化粧品など、生活文化の創造を目的としています。
この2つのブランドから、引き継がれてきた伝統を大切にする姿勢と、新しい挑戦に挑む方針が伺えますね。
ほかにも、海外市場への積極的な進出や、市場に合わせたブランド刷新にも力を入れていくよう。
長部訓子さんは、2021年当時以下のように発言していました。
21年は当社の創醸310周年の節目の年であり、外飲みでも家飲みでも「大関」のファンを増やす、そういった当たり前だが、地道な目線での活動をめざしたい。
Diamond Chain storeより引用
生活スタイルが大きく変化している現代、時代に合わせた経営を目指していくようですね。
日本酒業界への期待
「大関醸す 発酵鍋の素」に9種のスパイスを使用した「滋味和漢鍋」が仲間入り✨️
— 大関|日本酒メーカー🍶 (@ozeki_jp) August 7, 2025
8月25日から全3種を期間限定で発売します!
自社製酒粕を使用した発酵調味料で、手軽に本格的な味わいが楽しめます🍲 暑い時期はパスタやラーメンも作れる優れもの🙌 「滋味和漢鍋」は中華粥アレンジもおすすめです😋 pic.twitter.com/i6pTFB5z5u
日本酒業界は大きな変革の時期を迎えているようで、各社が様々な工夫をしています。
2024年、日本の伝統的酒づくりがユネスコ無形文化遺産に登録されました。
これにより、日本酒業も文化資産として見直されています。
また、日本酒市場としては、国内は縮小傾向なのに対し、海外では拡大している傾向があるよう。
そのため、国内市場拡大に向けた商品開発や、海外向けのブランド展開を行っているんだとか。
さらに、酒づくりにもAIやloTを導入し、発酵環境の最適化や品質安定化に役立てています。
日本の伝統技術として、今後の日本酒業界の成長に期待したいですね。
まとめ
今回は、長部訓子のwiki風プロフ・経歴まとめ!長部家の歴史についても!
〇長部訓子のプロフィール
〇長部訓子のこれまでの経歴
〇長部家の歴史とは
〇長部訓子のこれから
についてご紹介させえていただきました。
これからも大関の活躍に注目ですね!